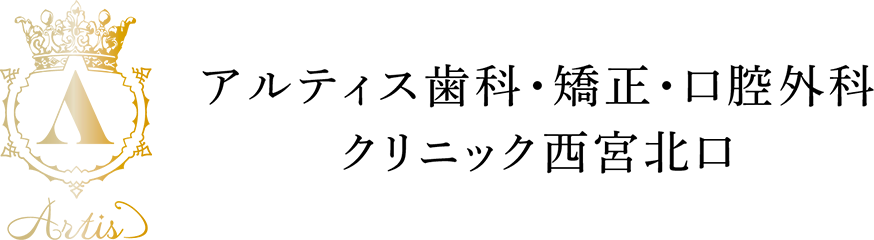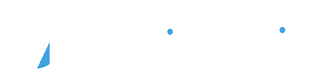歯周病って何?
歯肉と歯の境い目に見えるプラーク歯石といったお口の中や細菌がたまることによって起こる病気です。
ブラッシング時の出血や口臭、歯肉が赤いなどわかりやすい症状ですが、大きく膨らむうずくような痛みを伴わないことも多いために知らずのうちに進んでしまいます。
慢性的なによる腫れはやがて歯を支える 歯槽骨にまで影響し、歯槽骨が溶けて歯を維持することができなくなり、症状になると歯は脱落してしまいます。
一般的に歯周病とか、昔は歯槽膿漏(しそうのうろう)と言われてきました。 その後紹介する、歯根から感染する根尖性歯周炎と区別するために、歯の周囲の組織(歯周組織)から感染するので、辺縁性歯周炎とも言われています。
歯周病は慢性的な病気で一度罹ると完治する病気ではありませんが、歯科医院での専門的なケアと併せてそれぞれのお口の状況に合った正しいブラッシングにより改善・維持を続けることが出来ます。

歯周病を気にするには?
レントゲン検査や歯周ポケットの測定検査により、弱いところを歯科医師や歯科衛生士が確認し、不安のお口の状態に合ったブラッシング指導や歯石除去を行います。
専門的なケアを行うことにより口腔内を清潔にし、歯肉の腫れや口腔内の衛生度を一度に改善することができます。
さらに、必要に応じては専門的な歯周ポケット内の掻爬やGTR法(部分的に行った歯槽骨を回復させる再生治療)などの外科の処置を行うこともあります。
(※ただし、歯周病の状態によっては適応にならない場合もあります。) 残念ながらどうしても残すことができない場合には抜歯になることもあります。
しかし、一通りの歯周治療が終わっても、毎日のブラッシングを忘れたら、終わって帰ってしまいます。 指導を受けて自分に適したブラッシングの方法(①自分に合った歯ブラシを使う②正しく歯ブラシの持つ③正しい位置に歯ブラシを正しくetc)を続けていくことが大切です。
そうすれば、自然にきちんと磨けるようになり、歯肉はみるみる元気になります。 また、歯ブラシでは磨けないところは歯間ブラシ・デンタルフロス・部分磨き用の歯ブラシなどの補助器具も併用すると効果的です。
生活習慣の改善も歯周病予防の大切な方法と言います。例えば、私の毎日の生活の中にある歯周病にかかりやすい要素を取り除き、食生活を改善することです。繊維質やビタミンCが豊富でバランスの良い食生活を心がけましょう。
歯周病を悪化させる最大の要素の一つに喫煙があります。 喫煙により血流が低下し、口腔粘膜は酸欠状態や栄養不足になり、歯周治療の治療も悪く予防後もあまりよくありません。
喫煙の習慣がある方は是非禁煙をおすすめします。そして、歯周病菌に負けない身体の抵抗力をつけることも大切です。
以上のように健康的な生活習慣・食生活を送り、できれば2~3回の定期健診とあわせてクリーニングを受けることでお口の清潔を優先、現状維持を図り改善予防をしましょう。
もうひとつの歯周炎って何?

ところで歯肉にニキビのような腫れを見たことはありませんか?口内炎のようにも思われがちですが、潰れたり治ったと思っても再発したりする事があります。これは歯周炎の中でも根尖性歯周炎というものです。
辺縁性歯周炎と違って、歯根の中から感染するのです。
歯肉自体の固有の病気ではなく、歯髄や歯髄の管が細菌に侵され、歯の根の先端の外側、つまり歯槽骨まで当たった状態です。
貯めた膿に上皮が出来て袋状になると嚢細胞(のうほう)という、さらに治りにくいものになることもあります。
 レントゲン写真で見ますと、歯根の先端部分が黒く写っています。 慢性的なものと急性的なものがあり、①慢性の根尖性歯周炎ではあまり出現症状が無いことが多く、強く噛んだりすると歯が浮いたような違和感を感じることもあります。 を当然などと、抵抗力体調が低下すると、かなりに痛んだり大きな腫れとなることがございます。②急性の根尖性歯周炎では、歯が浮いたような感覚がはっきりとあり、痛くて噛み合わせる事が出来ません。歯根の先端で化膿し出口が無い場合にはズキズキと痛みがします。ひどい場合には顔やリンパ節まで発熱します。
レントゲン写真で見ますと、歯根の先端部分が黒く写っています。 慢性的なものと急性的なものがあり、①慢性の根尖性歯周炎ではあまり出現症状が無いことが多く、強く噛んだりすると歯が浮いたような違和感を感じることもあります。 を当然などと、抵抗力体調が低下すると、かなりに痛んだり大きな腫れとなることがございます。②急性の根尖性歯周炎では、歯が浮いたような感覚がはっきりとあり、痛くて噛み合わせる事が出来ません。歯根の先端で化膿し出口が無い場合にはズキズキと痛みがします。ひどい場合には顔やリンパ節まで発熱します。根尖性歯周炎を感じるには?
根尖性歯周炎の治療は、歯髄の管の中を再清掃していくのが基本です。感染により腐った歯髄や汚染物を取り除き、歯根の中を清掃し、繰り返し消毒していきます。
なかなか膿の袋が小さくなったり症状が改善しない場合には、外科手術で歯根の先端ごと膿や嚢細胞を取ったり、状態によっては抜歯する事もあります。
虫歯のようにハッキリとした痛みがあるので、かなり進んでいることが多いので、多少の違和感があればすぐにやることを推奨いたします。
症状が全くなくても神経の処置を受けた人はレントゲンで定期的な健診を受けて少しでも早期発見につながることがあります。